乽悘峴擔婰乿偦偺係
俹俀俁乣係係
 丂丂丂丂丂
丂丂丂丂丂
俹俀俁丂丂丂丂丂尦帯尦擭乮1864乯8寧
尦帯尦擭巕
敧寧廫擔
扷撨條屼帠崯搙嫗搒
曄摦擵媀僯晅旐栔
屼晄嫽摽嶳屼梐旐嬄弌
柧廫堦擔屼敪懌僯偰屼墇
旐梀彫惗 媀屼嫙旐嬄晅
岓帠
堦屼栚晅廜 妢尨敼擵彆
丂暔摢廜 栴揷拠塹椉恖
丂慻巕旐彚楢屼寈塹
丂僯偰旐旊墇岓帠
廫擔栭拞屼廻傢傝
僯偰弌懌岓帠
*1 亖昅幰丅懄偪攇揷梌巗偺偙偲丅
*2 亖旕堘傪専嶡偟庡孨偵曬崘偟偨娔嶡姱丅亙峕屗帪戙亜戝栚晅仺榁拞偵捈寢偟偰戝柤傪娔嶡丅栚晅仺庒擭婑偵捈懏偟偰婙杮側偳傪娔嶡丅
奺斔偺彅戝柤傕偙偺怑傪抲偄偨丅
*3 亖攱斔戝慻乮悮搈慻乯180愇乮攱斔媼榎挔傛傝乯丅
*4 亖媩慻丄揝朇慻摍傪棪偄傞栶怑丅
*5 亖攱斔戝慻乮斏戲慻乯254愇乮攱斔媼榎挔傛傝乯丅
拲37 亖挬掛偺挿廈斔捛摙椷偵懳偟偰丄挿廈斔偱偼斔榑偑暣憶偟偨偑丄摉帪嫳弴攈偑斔惌傪扴摉偟偰偄偨堊偵8寧2擔塃塹栧夘
乮塿揷恊巤乯傪偼偠傔暉尨丄崙巌偺嶰戝晇偍傛傃幊屗嵍攏夘丄抾撪惓暫塹偺擇嶲杁偺怑傪柶偠丄嶰戝晇傪巟斔摽嶳偵梐偗偰嬛琰偟偨丅弶傔塿揷塃塹栧夘偼摽嶳丄暉尨
偼挿晎丄崙巌偼惔枛偵暘娔偡傞曽恓偱偁偭偨偑攏娭愴摤偺嫲傟偑崅傑偭偰偄偨偺偱慡堳傪摽嶳偵憲傞偙偲偵側偭偨丅挿廈斔偼嶰戝晇偺嵾忬偲偟偰丄楺巑懘懠傪捔晱偡
傞偨傔偵忋嫗偝偣偨偵傕峉傢傜偢丄棃搰枖暫塹偺朶榑偵摨堄偟偰愴偄偵媦傃丄堌懡偔傕泜嫃偺暫酂傪彽偒嬍嵗偺摦梙傪堷偒婲偙偟偨奜丄搒偺恖怱婣岦偵戝奞傪惗偠偨丅
偦偺寢壥丄栄棙岞偼挬揋偺墭柤傪晧偆偙偲偵側偭偨丅偙傟偼孯椷偵傕堘斀偟偰偄傞丅峏偵堦扷愴憟偲傕側傟偽崻嫆抧揤墹嶳傪巰庣偡傋偒偲偙傠丄巆暫傕庢傝揨傔偢丄
懡偔偺巑懖傪巰彎偝偣丄晲婍傪幪偰偰恀偭愭偵揚戅偡傞偲偼慡偔埲偰孯椷傕憡棫偨偢丄屼摉壠偺晲埿傪鈗偟偨乧偙偲傪嫇偘偨丅偟偐偟丄嶰戝晇偼斔恇偲偼偄偊崱傗揤
壓偺嵾恖偱偁傞偐傜丄揤枊偺柦傪懸偮傋偒偱偁傝丄挿廈斔偑帺傜張敱偟偰偼側傜側偄偲偺媑愳娔暔傜偺堄尒偵傛傝摽嶳偍梐偗偲側偭偨偺偱偁傞丅
8寧2擔嶰戝晇偺怑傪柶偠丄堦嫇偺揯枛傪悇栤偣偟傔偨嵺偺栤愑忬偼師偺傛偆側撪梕偱偁偭偨丅
亀
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂塿揷塃塹栧夘
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂暉尨墇屻
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂殸巌怣擹
塃丂楺巑懘奜鐽晱擵偨傔丂嫗搒昞憡懾嫃岓媀偵岓摼偽屼殸壠擵屼啜擻條壜庢寁擵檤丂栂偵樢搰嵆暫塹丂朶榑偵摨堄偟丂朣柦擵楺巑朶幄擵暫偵堷揨傂丂悑堦滵岓抜巹擵
彂柺傪埲揤挬枊晎傊怽弌岓偵晅偰偼丂鐽晱擵怑偲偟偰朶潷擵幄摢偣偟傔丂忚嫲懡偔傕丂忋偵偟偰泜嫃擵暫酂傪彽偒丂嬍嵗擵梙摦傪抳偟丂壓偵偟偰搒壓恖怱焏岦擵戝奞
傪惗偠岓抜丂屼檁揳條寭偰擵屼惤堄偼撫彸抦丂嫳弴擵巚彚傪庢幐傂丂廔偵屼檁揳條傊挬揋擵柤傪晧偣岓偵憡醕傝丂柤媊晄憡棫丂斵惀憤偰屼孯椷擵巪偵傕憡攚偒懘嵾敎
戝偵岓檤擛壗旐憡怱摼岓嵠 婛偵滵憟偵媦岓摼偼丂揤墹嶳傪崻嫆偲偟丂壜憡曐擵檤丂巆暫傪晄揨丂巑懖擵巰彎傪晄栤丂澤懡擵婍夿傪庢幪丂堦斣偵戅懌棫岓抜丂慡埲屼孯
椷晄憡棫丂屼醕壠擵屼晲埿傪傕憡鈗偟丂懘嵾晄鏹岓檤擛壗旐憡怱摼岓嵠丂亁
側偍丄塿揷壠偺壠柤懚懕偵偮偄偰偼8寧5擔偺帪揰偱埨揼偺栚搑偑晅偄偰偄偨偲巚傢傟傞
亀丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂 塿揷塃塹栧夘
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂恊椶拞涹壠榁嫟
塃丂巚彚偵晄憡姁庯桳擵丂栄棙扺楬庣條傊旐惉屼梐岓栟壠嬝擵媀偼廳偒壠暱偵晅丂奿暿擵屼慒媍嬝傕桳擵帠偵晅嵟慜旐嬄暦抲岓捠丂淺埲拕巕惛師榊曗嵅偄偨偟丂屼梡
偵憡棫岓條怽崌丂惛乆怱攝娞梫擵帠丂崯抜壜怽暦巪岓帠
丂丂丂敧寧屲擔丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂亁
丂丂丂丂丂丂丂
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂乮弌揟亖乽杊挿夞揤巎乿戞係曇壓丂係俀暸乯
拲38 亖乽夞揤幚婰乿偵傛傟偽塃塹栧夘恊巤岞偵嫙曭偟偨幰偼孖嶳墺曘丄埨晉嬨榊暫塹丄壃栰欦嵍塹栧丄徏尨恗憼丄
愇愳姰憼丄拞懞摗攏丄屼攏壆慻堥媑偺7柤偱偁偭偨丅偙偺擔婰偺昅幰丄攇揷梌巗傪偼偠傔擔婰偵搊応偡傞憹栰枖廫榊丄懡崻塊堦丄嵅乆栘掑夘乮壃栰敼懢乯丄彫崙梈憼丄
徏尨懽憼丄徏杮桞巗丄昳愳椙彆側偳偼娷傑傟偰嫃側偄丅偙傟偼昞岦偒偺7柤偺奜偵壠拞偺懡偔偺恖偑堦峴傪暿峴摦偱巟墖偟偰偄偨帠傪帵偟偰偄傞丅
丂
俹俀係丂丂丂丂丂尦帯尦擭乮1864乯8寧
廫堦擔
摽嵅屼巭
屼廻丂丂丂墫壆媀暫塹
屼栚晅廻丂孠尨廳嵍塹栧
暔摢廻丂丂攱愳揙惸
彲壆丂丂丂捴丂枖幍
栚戙丂丂丂捴丂巗嵍塹栧
崱擔屼拫壝擭懞
彲壆丂丂丂攇懡栰婽嶰榊
丂丂丂丂丂丂丂丂丂晹壆
擖掄庡 丂丂丂丂丂丂巗尨幍榊嵍塹栧
廫擇擔丂摽嵅屼弌懌
桼僲栘梂 屼拫媥
*6*8*11 亖嶳岥導垻晲孲垻搶挰摽嵅丅塿揷偵岦偐偆崙摴9崋慄傪摽嵅偱嵍愜偟崙摴315慄傪峴偔偲壝擭宱桼恵嵅偵帄傞丅枖丄塃愜偡傟偽桵栘
(*11亖嵅攇孲摽抧挰桵栘)丄幁栰丄戝摴棦傪宱偰摽嶳偵帄傞丅恵嵅偐傜摽嶳傊偺奨摴嬝偼奣偹尰嵼偺崙摴315崋慄偺摴弴偱恵嵅仺栱晉(傗偳傒)仺壝擭(偐偹)
仺摽嵅仺桵栘仺幁栰(偐偺)仺戝摴棦(偍偍偳偆傝)仺搚嫃(枖偼壓徏)仺摽嶳偲恑傓丅搚嫃偼廃撿巗搚堜丅 杊挿棯抧恾嶲徠丅
*7 亖抧尦偱偼乽捴杮恮乿偲屇偽傟傞丅垻搶挰栶応岦偐偄偵尰懚偡傞媽壠丅
*9 亖壆晘偼尰懚偣偢嬐偐偵憼偺傒偑尰懚偡傞丅
*10 亖尰垻搶挰戝帤壝擭壓201偵壆晘偑尰懚偡傞丅
俹俀俆丂丂丂丂丂尦帯尦擭乮1864乯8寧
丂屼廻丂戝崟壆揱憼
丂彲壆丂嵵摗忢擵恑
幁僲巗 崱栭屼攽
丂屼廻丂彑娫揷怣塃塹栧
丂彲壆丂娾嶈
廫嶰擔幁僲巗屼敪夗
戝捠傝梂 屼拫媥
丂屼廻丂丂揷拞懛巐榊
廫巐擔嬇屼愭墇僯偰弌懌
巐帪搚嫃墂 枠旊弌摽嶳
撪棎桳擵岓條巕彸傝岓屘
懘抜憗懍孖墺 枠怽
尛彫惗憗懍摽嶳旊弌
挰栶強僯偰崯搙
*1 *4 *6 亖P24偺媟拲傪嶲徠丅戝摴棦揷拞壠偼尰懚偟側偄偑棿朙帥偵曟偁傝丅
*2 亖尰廃撿巗幁栰挰偵壆晘偑尰懚偡傞丅
*3 亖娾嶈憐嵍塹栧偺巕懛偱偼側偐傠偆偐丅娾嶈壠偺壆晘偼尰懚偣偢幁栰挰擾懞岞墍偵壆晘愓偺愇旇偁傝丅枖丄憐嵍塹栧偐傜巐戙栚偑
憖嬈偟偨娾嶈寽氣摪乮惢栻嬈乯偺峳傟偨壆晘偑幁栰挰偵尰懚偡傞丅
*5 亖屵慜10帪丅
*7 亖P23*1嶲徠丅
拲39 亖乽杊挿夞揤巎乿偺乽摽嶳撪鎌乿偵娭偡傞婰弎偼師偺捠傝丅
亀乧8寧9擔栭壨揷壚憼摍10悢恖榁恇晉揷尮師榊偺壠傪廝偆丅尮師榊彎傪栔傝偰摝傞丅婛偵偟偰壨揷傜摨巑7恖慜屻戇曔偣傜傟埥偼孻巰偟埥偼
嫢庤偵澦傞丅埬偢傞偵嫗搒曄屻摽嶳斔枓惓懎2攈傪惗偠懎攈偺椞懗晊揷乮晉嶳乯尮帯榊乮尮師榊乯梫楬偵棫偪枊晎偵垻晬偟偰鋺傕柶傟傫偲偡傞
偺鐟偁傝丅壨揷壚憼溗奡姮偊偢摨巙偲嫟偵晊揷乮晉嶳乯傪廝偄偟側傝丅斔棛搟傝偰懘搣梌傪戇曔偡丅壨揷偼堦偨傃扙杬偟恞偱曔傊傜傟偰崠偵搳
偠11寧24擔巃偵張偣傜傞丅堜忋桞堦丄杮忛惔丄愺尒埨擵忓丄怣揷嶌戝晇偼奆崠偵搳偠堜忋偼壨揷偲嫟偵巃偵張偣傜傟懠偼奆宑墳尦擭惓寧
14擔嫢庤偵澦傞丅峕懞旻擵恑偼8寧11擔弩怑壠偵琰偣傜傟梻12擔嫢庤偵澦傟帣嬍師榊旻枓峕懞偲擔傪摨偠偔偟偰澦傞丅擵傟傪摽嶳幍巑偲
徧偡丅梻宑墳尦擭6寧廆斔幊屗旛慜慜尨旻懢榊傪摽嶳偵尛傝扺楬庣偵愢偒晊揷乮晉嶳乯摍傪愃偗惓攈偺巑傪搊梖偣偟傓亁
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂乮弌揟亖乽杊挿夞揤巎乿戞巐曇壓77暸乯
拲40 亖柤偼拤憦丅弶傔梌師榊丄婰椷丄暯曘丄嬨榊嵍塹栧丅崋偼悡奤丅暥壔7擭乮1810乯11寧23擔恵嵅偵惗傑傞丅晝拤嵅丄曣偼
戝扟巵丅孖嶳壠墦慶偼塿揷寭棟嶰抝拤彑偺懛寭峧嶰抝寭拤丄愇廈孖嶳梂偵嫃廧偡傞傛偆偵側偭偰孖嶳傪巵偲偟偨丅塿揷巵偵廬偭偰恵嵅偵堏廧偡丅
墺曘偼恵嵅偺柤壠憹栰岇弐偺師抝偱偁偭偨偑拤嵅偵抝巕偑側偐偭偨偺偱墺曘傪梴巕偲偟偨丅幚偺曣偼攇揷搶嶌寭屨偺柡偱偁傞乮拲俇嶲徠乯丅恖偲
側傝桪傟偰偝偲偔丄怱偑峀偔帠暔偵捠払偟偰偄偨丅暥晲偵桪傟暫朄孯妛偵捠偠偰偄偨丅壝塱5擭摉栶丅壝塱6擭乮1853乯埲屻丄崙偺撪奜偼懡
擄傪嬌傔傞偑丄偙偺帪偵摉偨傝椞庡恊巤偼斔偺廳栶偲偟偰崙帠偵專恎偡傞丅偙傟傪墺曘偼曗嵅偟恑傫偱崙柦偵巀惉偟枖偁傞帪偼戅偄偰懞惌偵摉偨
偭偨丅宑墳尦擭乮1865乯懜峜攈偲嫳弴攈偺榑憟偑婲偙傝乮恵嵅撪鎌帠審乯摉栶丄擭峴帠壛敾丄屼彑庤屼梡寽傝偺栶怑偵偁傝嫳弴攈偱偁偭偨墺
曘偼丄偦偺帪梂偺幏惌偵偁偭偨偨傔偵懜峜攈偺悽偺拞偵側偭偨帪丄怑傪捛傢傟偨丅梻擭嵾傪嫋偝傟偨偑嵞傃梫怑偵暅婣偡傞偙偲偼側偐偭偨丅斢擭
偼巕掜偺嫵堢偲帊暥偺憂嶌偵愱擮偟偨丅
丂丂丂丂丂丂丂丂乮弌揟亖壃栰敼懢乽徏撴堚峞乿丄乽恵嵅堢塸娰乿79暸乯
俹俀俇丂丂丂丂丂尦帯尦擭乮1864乯8寧
塃塹栧夘揳屼摉斔旐旊墇
岓僯晅堊愭墇旊弌岓娫
屼堷庴擵屼廜拞傊
抳憡懳搙抜怽擖岓張
彮滼岓條怽僯晅棫廻
憡峔滼嫃岓張
栘懞埨戝晇 偲怽恗嶲
傝岓屘抳憡懳
塃塹栧夘揳崱擔旐旊墇
岓娫泋儗僯偰屼堷庴
憡惉岓嵠偺抜憡恞
岓張彮乆敿搑擵媀傕
桳擵岓偊嫟扅崱傛傝
抳巇峔屼媞壆 僯帶
*8 亖P12 *3嶲徠丅
*9 亖P28嶲徠丅摽嶳斔偺乽屼彑庤岦榙偺巇弌尦乊栶僇乿偲偁傝丅
*10 亖梐傝恖丄嵾恖側偳傪廂梕偡傞寶暔丅
俹俀俈丂丂丂丂丂尦帯尦擭乮1864乯8寧
屼堷庴壜巇桼旐怽岓僯晅
彸抦擵抜憡怢
奿暿屼柀嬝柍擵岓
嵠偲憡恞岓張崯撪
墬撪椫彮偟條巕桳擵
岓偊嫟憗懍抳庢嶌
奿暿柀嬝柍擵屼堷
庴壜巇桼僯晅懘抜枖乆
孖墺枠怽尛岓帠
堦夁傞敧擔崙巌怣擹條
丂屼墇旐惉嶐廫擇擔暉
丂墇屻條 屼墇旐惉岓條巕
丂僯晅憗懍暉尨屼廻
丂旊弌嵅乆栘掑夘 抳
*1 亖弎傋
*2 亖嵎偟巟偊
*3 亖摽嶳撪鎌偺偙偲丅P25拲39嶲徠丅
*4 亖庢傝慤偄
*5 亖P22 *6嶲徠丅
*6 亖P13 *9嶲徠丅
拲41 亖壃栰敼懢(1835-1885)偺偙偲丅 弶傔偺柤傪婤丄帤傪帪峴偲偄偆丅塿揷巵壠恖丄壃栰埨愊偺戞嶰巕
偲偟偰恵嵅偱惗傑傟偨丅梒帣傛傝妛栤偵椼傒丄堢塸娰偺彫崙梈憼傜偵妛傫偩屻丄媑揷徏堿偺栧壓惗偲側傞丅峏偵嫗丄峕屗偵弌偰椡傪晅偗偨屻丄攱斔壠
榁暉尨巵偺庲巘偺嵅乆栘壠偵擖壠丄嵅乆栘掑夘偲柤慜傪曄偊偨丅尦帯尦擭丄敻屼栧偺曄偱偼暉尨巵偵廬偭偰嫗偵忋傝孯帠偵嶲壛偟偨丅偦偺屻丄攱斔偺
嶳岥柧椣娰嫵庼丄嫗搒巘斖妛峑嫵桜傪楌擟丅娍帊偵挿偠偦偺挊嶌偼乽徏扥堚峞乿偲偟偰巆偝傟偰偄傞丅丂挿彈偼塿揷愽乮奀憼埩乯偵壟偄偩丅
丂丂丂丂丂丂丂丂乮弌揟亖乽恵嵅堢塸娰乿俉俀暸媦傃侾侽侾暸埲壓乯
俹俀俉丂丂丂丂丂尦帯尦擭乮1864乯8寧
憡懳屼條巕偄嬋憡彸傝
懄崗婣棃屼
媞壆擵曽岊憡岓帶
屼媞壆傊嶲傝堦尒岓帠
扷撨條曢榋帪屼拝
旐梀岓屘彫惗 屼幃戜
屼嬤旊弌摽嶳傛傝僴
堦岦栶恖弌晜柍擵
屼撪椫杮恮 摨條偵
憡怱摼抳堷庴屶岓
條偲偺媀僯帶扅屼彑庤
岦榙偺巇弌尦乊栶僇
栘懞埨戝晇涹杮恮
摗堜暥帯榊 偲怽恗
*7 亖徻偟偔嵶偐側偙偲丅
*8 亖屵屻榋帪丅
*9 亖攇揷梌巗丅P24 *1嶲徠丅
*10 亖P3 *12嶲徠丅
*11 亖椃娰乽杮恮乿偺偙偲丅
*12 亖摽嶳斔巑丅
拲42 亖嵅乆栘掑夘乮壃栰敼懢乯偑13擔偵暉尨屼廻傊丄懡崻塊堦偑14擔偵崙巌屼椃娰傊偦傟偧傟晪偄偰懠壠偺榖傪暦偄偰偄傞丅
乽寧斣擔婰乿偺8寧16擔偺婰榐偵傛傞偲乽屼嫙偺撪傛傝怽墇僔岓庯偼丄暉尨墇屻條屼壠棃拞堦摑丄扱婅偺媀怽弌岓條巕僯晅丄墬屼撪椫傕壗偦媂晘
婥晅嫟屼嵗岓僴僶扱婅偺媀壜旐嬄弌丄墬摉栶拞僯愡妏怽崌尒岓偲偺帠僯屼嵗岓乿偲弎傋傜傟偰偄傞丅乽夞揤幚婰乿偵傛傟偽偙偺屻丄塿揷壠拞偐傜傕
暉尨壠偵曧偭偰壗搙偐扱婅彂傪弌偡偙偲偵側傞偑丄愭偢17擔戝捤楺峕戭偵偍偄偰屼庤夢戝夛媍偁傝丄梂惌摪偵懳偟偰扱婅彂採弌偵偮偄偰堄尒彂傪
弌偟偨丅偦偺屻戝慻巐慻傕摨條偺寶尵傪偟偨偲弎傋傜傟偰偄傞丅乮拲44嶲徠乯
俹俀俋丂丂丂丂丂尦帯尦擭乮1864乯8寧
弌晜擵帠
栭拞懡崻塊堦 崙巌擵
屼椃娰旊弌屼條巕
彸傝彯枖柧擔摉斔傊
屼堷搉憡惉岓敜僯帶
屼嫃強帠偺奜尩崗
擵桼彸傝婣墬屼撪椫
屼嫙拞戝抳嬃湵
廌捝擄姮旊嫃岓帠
廫巐擔
屼媞壆屼懾棷
僗僒屼旘媟旐嵎曉
摉栶廜堧恖屼梡恖堦恖
*1 亖偒傃偟丄傓偛偨傜偟丄嶴崜. (杊挿夞揤巎丂戞巐曇壓榋 P308)乽戉拞偺巑摿偵摽嶳丄娾崙偵晪偒嶰戝晇傪扗偆偺嫇偵弌傫偲偡傞偵帄傟傝丂
寈曬憡宲偱攱偵払偡乿偲偁傝丄傑偨摨P313偵偼乽柧椣娰偵嶲廤偺憇巑200梋恖傪摽嶳偵攈偡乿偲偁傝丄斔惌晎偼彅戉偺朶敪偵旛偊偰寈旛傪尩廳偵偟偨丅
拲43 亖乮杮柤廫榊乯乮1831乣1910乯丅枊枛恵嵅偺柤寱巑偲偟偰抦傜傟丄揤曐2擭乮1831乯惓寧23擔恵嵅偵惗傑傟傞丅懡崻壠偼塿揷11戙
寭尒偺嶰抝埳摛庣寭惌偺巕懛偱偁傞丅峕屗偺乽楙暫娰乿偵擖栧丄惸摗栱嬨榊偵恄摴柍擮棳傪妛傃丄枖崃恄堿棳偲偦偺嬌堄乮柶嫋奆揱乯傪嬌傔偨丅摨栧乮楙暫娰乯
偵2嵨擭壓偺宩彫屲榊乮栘屗岶堯乯傕偄偨丅枊枛寖摦偺崰戝偄偵妶桇偟丄媫恑攈乮惓媊攈乯偐傜壐寬攈乮懎榑攈乯偵梌偟偨偲栚偝傟偨丅柧帯偵擖偭偰崅枔懞
乮尰傓偮傒懞乯偵廧偄傪堏偟偰丄摴応傪奐偒丄暥晲偺摴傪嫵偊丄栧壓傕懡偐偭偨丅柧帯42擭3寧15擔乮79嵨乯杤丅
丂丂丂丂丂丂 乮弌揟亖乽懡崻壠屗愋摚杮乿乽懡崻塊堦崃恄堿棳柶嫋乿乽塿揷巵偲恵嵅乿195暸乯
拲44 亖9寧4擔丄摉擔偺寧斣戭栰懢榊丄撪摗梌嶰嵍塹栧偑楢柤偱塿揷嶰榊嵍塹栧乮梂惌摪乯偵採弌偟偨戝慻偺扱婅彂埬偵偼師偺傛偆偵弎傋偰偄傞丅
亀乧捛乆摽嶳屼堷庴偺屼條巕彸傝岓張丄惤僯尩嬛偺屼峔慡廁崠摨條偺媀偵偰丄壠棃堧恖旐巆抲岓偊嫟庡恖梡曋摍傕堦岦晄摼巇丄挬梉偺栚捠傝傕憡惉晄怽丄
恏鋮偺掱怺偔旐嶡岓丂慠張丄塃塹栧夘揳嬤棃昦恎僯偰嫻捝娫乆嵎婲傝旐抳擄媀帠僯岓偊僴扅崱偺捠傝僯偰偼恎柦庢椊偺媀傕擛壗壜桳擵嵠丂妿墬晹壆岦僯
摽嶳偺條巕捛乆旐抳彸抦晄旐堊埨怮怘嫟嬯怱偺梋傝摉愡昦婥嵎婲斵惀偺師戞尒暦巇岓偱偼惤僯恇壓偺垼捝晄夁擵曭懚抦岓亁
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂乮弌揟亖乽寧斣擔婰乿乯
側偍丄杮斔偵採弌偝傟偨壠恇堦斒彁柤偺扱婅彂偵塿揷壠拞偲偟偰偺敻屼栧偺曄偵懳偡傞峫偊曽偑師偺條偵弎傋傜傟偰偄傞丅
亀乮慜棯乯崱斒嫗巘曄摦僲晪僯晅晄恾屼尩姊擵恎僩旐憡惉惤埲巆擮帄嬌僯曭懚岓丅栟墬忋崙懘愡惌晎擵屼寶媍屼惉嶼幰擛壗僯僥屼嵗岓嵠擄検岓摼嫟丄
旝恇擵娗尒僯僥僴丄懐搣汙寁儝岻儈惓楬儝嵡僊丄媝僥斁儝埲僥摙敯僲捄儝岊僀丄揤棾帥丄揤墹嶳僲彅惃僴摙庤嵎岦岓庤敜丄婋媫扷梉僯憡敆儕丄戅僥扱婅
僲媀僴嵎抲丄恑帶鎛懐僲応崌僯嵎妡儕幚埲媊怱寖楏丄晄姮暜滎丄娽慜僲懐搆堊崙壠鎛柵擵媍榑僯僥堊桳擵嵠丄弅儖張塃堦嫇儓儕屼崙屼戝帠擵屼応崌僯棫峴
岓抜僴曭嫲擖岓丅嫀撫慜審怽忋岓庡恖擭棃僲慺巙僯僥幰丄扅拤媊堦搑僯僥懘帪僲慂鑧晄旐峴撏廔僯懐寁僯懧儕岓媀幰岥惿僔僉師戞丄惀僩怽僗儌壗懖曬崙擵
扥怱憡壥僔搙旐懚擖丄媝僥寉嫇僯憡惉岓愡丄墬崯抜幰崱峏殐鋊乮僛僀僙僀乯僲巚巆夨柍尷岓摼嫟丄昄桧庡恖墬懚椂幰恀怱擵堦揙儓儕旐摜崬岓栿僯僥丄
堦焲僲晄拤愡旐嵎峔岓嬝柍擵惵揤敀擔儝柨僸丄桳拤巙帶柍巹怱抜丄撫晄媦旝恇摍忢乆晬揧尒暦岓媀丄墬姱晎儌惀枠僲屼曭岞怳屼庤摉儌壜桳擵媊僯曭懚岓丅丂
廇僥僴崯搙僲嵾忬愒怱拤丄晄拤擵張懘偺棓鎇屼楓嶡旐惉壓丄曃僯嶲儕妡儕屼澪暘儝埲僥丄捛乆屼姲揟僯旐張岓條屼張抲旐惉壓岓僴僶丄墬恇摍崯忋僲屼峖壎
憮奀桺愺僋壜曭姶媰岓丅嫀撫扅崱庡恖擵桯廁懘壢儝埲僥屼崙擵屼柤暘儝旐惓岓媀丄柍梋媀師戞丄墬庡恖幰嬣怲旐旊嫃丄桺峏曬崙擵堦抂僯憡摉儕岓摼嫟丄
婔墳儌崱斒擵媀幰帪強儝岆儔儗岓堦搑僯僥堊崙壠焲椥僲巹嬋柍擵抜僴崕崕屼曎暿儝埲僥屼姲桮僯棫峴岓條丄屼幏寁擵掱曭扱婅岓丅乮屻棯乯亁
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂 丂乮弌揟亖乽夞揤幚婰乿乯
俹俁侽丂丂丂丂丂尦帯尦擭乮1864乯8寧
嵎弌擵媀怽嶲傝岓帠
栭拞屼栚晅廜暔摢廜
椉恖屼媞壆旐嶲柧擔
摉斔屼堷庴憡惉
岓抜旐怽岓帠
壩媫愇愳姰憼 嶳岥
昞傊旐嵎墇揤栰尓媑
寭帶撪墢桳擵岓僯晅
惌帠摪條巕彸傝婣
岓條旐嬄晅岓帠
彫崙梈憼棃
廫屲擔幍帪
屼栚晅廜暔摢廜屼媞
壆旐嶲慟屼堷庴憡惉
*2 亖P23 *2嶲徠丅
*3 亖P23 *4嶲徠丅
*4 亖恊巤岞偺摽嶳桯暵偵悘峴偟偨俈柤偺壠恇偺侾恖丅 恵嵅塿揷壠拞巑丄10愇丅P23拲38嶲徠丅
*5 亖攱斔惌柋堳丅塃揷栄棙壠妛暥摪偺嫵巘丅
*6 亖屵屻4帪丅
拲45 亖帤偼晲淪丄弶傔偼崉憼偲偄偭偨偑晝偺柤傪巏偄偱梈憼偲柤忔偭偨丅崋偼悡梲丅7嵨偱晝傪幐偄嬯妛偟偨偑19嵨偱峕屗偵棷妛丄
徆暯峑傪懖嬈屻埨堜拤暯偺栧壓惗偲側傝丄悑偵戝妛摢偺椦娎惸偵擣傔傜傟偰帢撉偲側偭偨丅懜峜偺巙偑嫮偔丄傑偨壼埼偺奐敪傪彞偊偰扨恎壼埼偐傜姃懢偵
搉傝帇嶡丄杒偺庣傝偺堊偵撛揷暫偺攈尛傪愢偄偨丅丂恵嵅傪棧傟偰10擭屻偺壝塱4擭恵嵅偵婣傝堢塸娰偺妛摢偲側傝丄恖嵽嫵堢偱塿揷恊巤偺婜懸偵墳偊偨丅
媑揷徏堿丄憁寧惈偲怺偔岎嵺偟丄徏堿偲巙傪捠偠偰栧惗偺岎姺傪峴偭偨丅暥媣2擭丄斔庡栄棙岞偑楍斔偵棪愭偟偰岞晲崌懱塣摦傪婲偙偟偨偺偱恊巤偼旈枾
偺栶栚傪懷傃偰忋嫗偟偨偑丄偙偺帪梈憼傪彚弌偟偰梡恖偲偟偰枾偐偵彅斔偲岎徛偝偣偨丅尦帯尦擭媣嶁尯悙偲嫟偵巙巑傪廤傔偰揤墹嶳偵恮傪晘偒烴堜朸偲
嫟偵孯娔傪柋傔偨偑丄敻屼栧偺曄偱愴偄偵攕傟偨丅偙偺愑擟傪栤傢傟偰椞庡恊巤偑摽嶳偵偍梐偗偲側傞傗丄戝扟杘彆傜偲嫟偵幍嫧乮摉帪屲嫧乯傪梚偟偰
庡孨傪媬弌偣偟傔丄媊婙傪東偟偰擇廈偺惓婥夞暅傪恾偭偨偺偱丄瀛嫃傪怽偟晅偗傜傟偨丅
丂 丂丂丂 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂 (弌揟亖乽恵嵅堢塸娰乿70暸)
俹俁侾丂丂丂丂丂尦帯尦擭乮1864乯8寧
岓條巕偺屘屼嫙壜巇桼僯晅
懄崗屼嫙懙僯偰憤帩
堾傊屼弌旐梀岓張幃
戜儓儕忋屼堧恖屼捠旐梀
屼嫙拞幃戜
僲娫枠旊捠傝滼嫃岓張
屼栚晅廜暔摢廜堷庴擵
栶恖傊旐抳憡懳彮娫憡
桳擵屼堷搉憡嵪岓焍
屼栚晅廜暔摢廜旐堷庢
岓帠懘愡梡払
堧恖巆抲 懘梋嫙恖悢
憗懍堷庢岓條偲擵媀僯
屼嵗岓
*1 亖憏帩堾丅塿揷恊巤乮偪偐偺傇乯愗暊偺抧丅崙巌怣擹偑愗暊偟偨悷愹帥偲偲傕偵柧帯弶擭偵夝曵偟敤抧偲側偭偨丅尰嵼丄摽嶳巗栄棙挰俁挌栚栄棙
儅儞僔儑儞妏偵偁傞乽塿揷塃塹栧夘帓櫃偺抧乿偺愇旇偐傜搶傊侾挌偺強偵偁偭偨丅幨恀34丄35嶲徠丅
*2 亖偦偺堧恖偺恖慖偵偮偄偰乽埨晉嬨榊暫塹偦偺愶偵偁偨傝懠偼摽嶳巗奨傊嶶嫃愽暁偣傝乿偲偁傞丅乮乽夞揤幚婰乿傛傝乯
俹俁俀丂丂丂丂丂尦帯尦擭乮1864乯8寧
孖嶳墺曘彫惗 椉恖
斵曽堷庴擵栶恖曅壀
憏塃塹栧 丒埦壆梌巐榊
偲乮怽乯恗傊抳憡懳堦墳擵
抳垾嶢堷庢岓帠
忋屼堧恖憡巆抲屼嫙
恖悢堷庢擵張晄姮
廌捝擄幨昅
廫榋擔
彫崙孨屼媞壆嶲傝崱擔
堦娧栰 枠婣岓抜憡怽
岓帠
屼嫙恖悢拞屼媞壆
*3 亖攇揷梌巗丅P23 *1嶲徠丅
*4 亖摽嶳斔巑丅
*5 亖摽嶳斔巑丅
*6 亖尰嶳岥巗偺導摴197崋増偄塿揷椞旘抧丅 杊挿棯抧恾嶲徠丅
俹俁俁丂丂丂丂丂尦帯尦擭乮1864乯8寧
懾棷僴晄憡惉媀僯晅
挰廻媑壆栱暫塹曽枠
堷庢屼榋広巐恖崱挬
弌懌僯僥僗僒傊旐嵎曉岓帠
廫幍擔
崱挬徏杮桞巗丒懡崻塊堦
徏尨懽憼拞娫巐恖
屼奐嶌抧崀徏傊嶲傝岓帠
屼淃拞娫栱彆僗僒傊旐嵎曉
摉栶堧恖屼梡恖堧恖
彚弌怽嶲傝嫃岓張崯抧
帠擵奜尩廳擵條巕僯晅
扅崱旐旊弌岓帶僴晄媂
岓娫屼堧恖僴壓徏屼弌
*1 亖斔揁側偳偵擖傝偒傜偢挰偵廧傓斔巑丅
*2 亖摽嶳斔巑丅
*3 亖奒媺昞偱偼夗饽扴偓偺偙偲丅悈媯傒傗嬳巊側偳傕偟偨丅6広偵払偡傞戝抝傪堄枴偡傞丅偺偪丄戞4戝朇慻丅乽棨広乿偲傕丅
*4 亖乽塿揷巵偲恵嵅乿P199偺巐嫬愴憟(愇廈岥偺愴)偱愃岓傪扴摉偟偨丅
*5 亖P29 拲43嶲徠丅
*6 亖塿揷壠恇丅
俹俁係丂丂丂丂丂尦帯尦擭乮1864乯8寧
屼堧恖嶳岥屼弌僯偰
宍惃屼扵嶕旐惉岓
條怽嶲傝岓帠
廫敧擔
嶐栭憹栰枖廫榊壓徏枠
棃拝擵桼怽棃
埨晉嬨榊暫塹崱擔憤帩
堾岎戙擵媀憡塣婣岓
屘憗懍昳愳椙彆旐嵎墇
岓帠丂憤帩堾尩
崗擵條巕嬨榊暫塹傛傝
彸傝晄姮垼捝師戞栫
斢崗憹枖廫榊壓徏儓儕
棃
*7 亖塿揷壠拞巑乮屼庤夢慻乯丄19愇乮恵嵅塿揷壠暘尷挔乯丅P23 拲38嶲徠丅
*8 亖塿揷壠恇丅宑墳2擭6寧(1866)丄巐嫬愴憟偺嵺愇廈岥偺攝旛偵偮偒恵嵅戉杒戞堦戝戉堦斣戝朇巜椷偵擟偠偨丅
拲46 亖廃撿巗偺搶偵椬愙偡傞( 杊挿棯抧恾嶲徠)丅悇屆揤峜17擭(609)偵乽戝惎廃杊崙搒擹孲榟摢彲惵桍塝
徏庽忋偵幍拫栭妐偲偟偰愨偊偢丅偙偙偵抧柤傪崀徏丄壓徏塝偲尵傢傟偨乿偲偺崀徏恄幮偺幍惎崀椪揱愢偑偁傝丄杒扖惎偺揤壓偭偨徏偵場傫偱惵桍塝偺抧柤傪崀徏
偲夵傔偨丅屻偵壓徏偲彂偔傛偆偵側偭偨丅昐嵪傊偺墲棃偺梫峘偩偭偨偙偲偐傜丄昐嵪捗偑壓徏偵側偭偨偲偺愢偑偁傞丅
丂 丂丂丂丂 丂丂丂丂丂丂丂 (弌揟亖乽嶳岥導偺楌巎嶶曕乿67暸乯
俹俁俆丂丂丂丂丂尦帯尦擭乮1864乯8寧
廫嬨擔
崱挬憹孨娗徏枠
婣愇愳姰憼嶳岥傊
旐嵎墇岓張嶳岥僯帶
屼枛壠條儓儕屼梡桳擵
堦墳僗僒傊婣崱擔慟
唰嫋弌晜擵帠揤栰
尓媑儓儕嶳岥條巕偄嵶
彸傝婣岓帠
擓擔
擓堦擔
埨晉嬨榊暫塹丒愇愳姰憼
拞懞摗攏娗徏傊峴
彫巕桳梡帠帶摨峴
僯偰嶲傝岓帠
*1 亖塿揷壠恇丅P23拲38嶲徠丅
拲47 亖杮壠攱栄棙壠丄枛壠挿晎栄棙壠丄枛壠摽嶳栄棙壠丄枛壠惔枛栄棙壠丄枛壠娾崙媑愳壠丄枛壠彫憗愳壠丄堦栧嶰媢幊屗壠丄堦栧塃揷栄棙壠丄
堦栧岤嫹栄棙壠丄堦栧媑晘栄棙壠丄堦栧垻愳栄棙壠丄堦栧戝栰栄棙壠丄塱戙壠榁恵嵅塿揷壠丄塱戙壠榁塅晹暉尨壠傪乽堦栧敧壠乿偲尵偭偨丅偙偙偱
乽屼枛壠條乿偲偼摽嶳栄棙壠偺偙偲偱偁傠偆丅
俹俁俇丂丂丂丂丂尦帯尦擭乮1864乯8寧
崱擔泋儗傕娗徏枠旊墇
妎屽僯屼嵗岓張彮
條巕桳擵孖嶳涹
彫巕丒拤擵忓嶰恖巆岓帠
斢崗憹孨摨峴僯僥
娗徏儓儕旊婣岓帠
擓擇擔
憹孨嶳岥枠峴
崱挬屼栶強挰曭峴
傛傝嫙巆恖悢憗乆
椞暘傊堷庢岓條怽
棃岓帠
屼栭嬶棃
*2 亖P4嶲徠丅
俹俁俈丂丂丂丂丂尦帯尦擭乮1864乯8寧
擓嶰擔
屵慜儓儕孖廸晝彫巕涹
拤擵忓嶰恖娗徏傊
旊墇岓帠
擓巐擔
屵慜崙巌屼壠棃桘
僲愽暁擵巑嵅乆栘徦堦榊
儓儕嶰懢晇峕屗旐嵎曉
懌偟晽昡桳擵條怽
棃懄崗懡崻塊堦丒
愇愳姰憼嶳岥傊
旐嵎弌慒媀憡惉岓帠
擓屲擔
徏尨懽憼摽嶳堛
巘椦椙塿曽傊旐嵎墇岓帠
*1 亖P4嶲徠丅
*2 亖尰廃撿巗搾栰丅屆偔偐傜偺壏愹抧偱寴揷巵嵣抧丅
*3 亖崙巌怣擹壠恇丅婏暫戉偵擖傝暥媣尦帯偺嵺壓娭偺恮塩偱峴摦偟偨丅偦偺屻傕奺強偵弌摦偟怣擹偵廳梡偝傟偨丅
柧帯偵擖傝丄嬼乆扙戉偺曄婲傝丄庱杁幰偲偟偰摨3擭9寧26擔嶳岥峹奜旳懞挿幰尨偵偰孻巰丄嫕擭29嵨丅
*4 亖塱戙壠榁恵嵅塿揷壠塿揷恊巤乮偪偐偺傇乯丄塱戙壠榁塅晹暉尨壠暉尨尦鷟(傕偲偨偗)丄婑慻崙巌怣擹恊憡偺栄棙壠嶰壠榁偺偙偲丅
*5 亖徏尨懽憼偑椦椙塿傪朘栤偟偨棟桼偼晄柧丅偟偐偟丄塿揷塃塹栧夘偑嫻捝傪姵偭偰偄偨乮P29拲44嶲徠乯偲偄偆偐傜丄
庡恖偺帯椕憡択偵峴偭偨壜擻惈偑崅偄丅
俹俁俉丂丂丂丂丂尦帯尦擭乮1864乯8寧
擓榋擔丂崱挬昳愳椙彆
憤帩堾儓儕壩媫僯旊
婣娗徏僯愽暁擵巑
桳擵岓抜屼栚晅廜
暦崬憡惉慒媀憡惉
岓條巕僯屼嵖岓娫憗乆
堷庢岓抜壜慠桼栘懞
埨懢晇傛傝憡庼岓桼僯
晅旊婣岓抜怽帠
屘泋儗傕怽崌憗懍
抳巇搙婣岓帠
埨晉嬨榊暫塹椙彆戙
偲偟偰憤帩堾旐嵎墇
*6 亖P34*8嶲徠丅
俹俁俋丂丂丂丂丂尦帯尦擭乮1864乯8寧
徏杮桞巗丒徏尨懽憼
椉恖偼崯娫嶳岥傊嵎弌抲岓
懡崻塊堦丒愇愳姰憼
枹婣晄怽岓屘嶳岥傊
旐嵎曉岓帠
栭拞恵乆杻懞傑偱
婣廻壆憡恞岓張
柀僯帶柍擵帠僯晅
忛摗巐榊寭帶屼弌擖
僲媀僯晅斵曽堦廻擵帠
擓幍擔
憗挬僗乀儅弌懌屵
慜幁僲巗僯帄傝
彑娫揷怣塃塹栧曽傊
*1 亖尰廃撿巗恵乆枩杮嫿丅栄棙尦廇偺屆愴応徖忛驿偑偁傞丅 杊挿棯抧恾嶲徠丅
*2 亖晄柧丅
*3 亖幁栰偺廻壆乮P25*2嶲徠乯
俹係侽丂丂丂丂丂尦帯尦擭乮1864乯8寧
棫婑岓張帠擵奜
旐棷岓懘忋懡崻塊堦丒
愇愳姰憼枹婣
晄怽岓屘堊懸崌堦擔
抳懾棷岓帠
娍梲帥杧偸偒堦
尒懘奜尒暘
擓敧擔
幁僲巗弌懌
惗塤巭廻
擓嬨擔
敄曢僗僒婣拝
捈條惔悈傊孖墺偺
*4 亖惔悈塿揷壠偺偙偲丅摉庡偼榁恇塿揷嶰榊嵍塹栧丅
拲48 亖搒擹孲幁栰挰忋幁栰偺椪嵪廆幁墤嶳娍梲帥偼墳埨7擭(1374)寶棫偱丄彟偰偼枛帥350儠帥偺屆檵丅帥揱偵傛傟偽戝撪惙尒偑梡摪柧婡慣巘
傪彽偄偰憂寶偟偨偲尵傢傟傞偑丄擭戙偐傜偡傟偽戝撪峅悽偺帪戙偵摉偨傞丅愇掚偲惛恑椏棟偑桳柤丅杧偸偒偼娍梲帥嫬撪棤庤偵偁傞挭壒摯偺偙偲丅彸墳3擭(1654)丄
幁栰偺廧恖娾嶈憐嵍塹栧乮1598乣1662乯偑巹旓偱4擭偺嵨寧傪旓傗偟偰姰惉偟偨恖岺悈楬丅慡挿270嘼丄僩儞僱儖晹暘偼88嘼丅偙傟偵傛傝21挰曕梋偺戜抧峩嶌偑
壜擻偲側傝丄堸椏悈傪嫙媼偟偨丅
丂丂丂丂丂乮弌揟亖乽嶳岥導偺楌巎嶶曕乿84暸丄乽嫿搚巎帠揟丂嶳岥導乿丄乽杊挿晽搚婰乿丄枛帥悢偼捈愙帥偵徠夛偟偨乯
俹係侾丂丂丂丂丂尦帯尦擭乮1864乯8寧
摨摴僯偰嶲傝條巕
憡払岓帠
夾擔
崱挬
屼揳旊弌屼條巕
怽忋岓帠
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂 姰
俹係俀丂丂丂丂丂尦帯尦擭乮1864乯11寧
拲49 亖尦帯尦擭11寧丄戞堦師挿廈惇敯偺枊孯偑峀搰偵廤寢偟偨丅敻屼栧偺曄偵攕傟丄娭栧奀嫭偱偺澋埼愴偵嶴攕傪媔偟偨
挿廈偺愴椡偼嬌搙偵掅壓偟偰偄傞丅偙傫側帪枊孯偵峌傔崬傑傟偨傜傂偲偨傑傝傕側偄丅愑擟傪栤傢傟偰丄偦傟傑偱斔撪偺幚尃傪埇偭偰偄偨媫恑攈偑
屻戅偟丄戙傢偭偰懎榑攈偲屇偽傟傞柛棞摗懢傜偺曐庣攈偑惌柋傪扴摉偟偨丅枊孯偺嶲杁偲偟偰峀搰偵棃偨戝搰媑擵彆乮惣嫿棽惙乯傕丄挿廈偲愴壩傪
岎偊媇惖幰傪弌偟偨偔側偄偲峫偊偰偄偨偐傜丄娾崙斔偺媑愳宱姴傪捠偠偰丄敻屼栧偺曄偺愑擟幰偱偁傞塿揷塃塹栧夘丄崙巌怣擹丄暉尨墇屻偺嶰壠榁
偺庱傪嵎偟弌偟丄挿廈偺幱嵾偺堄傪昞偟偰偼偳偆偐偲偄偆丅懎榑攈偺斔挕偼憗懍嶰恖偵愗暊偝偣傛偆偲偡傞丅偟偐偟丄斔撪偵偼斀懳偺惡傕嫮偔丄棳愇
偵柛棞傕嬯椂偡傞偑丄悑偵11寧11擔偐傜12擔憗嬇偵偐偗偰嶰壠榁偵巰傪柦偠偨丅
傑偨塃塹栧夘偵愗暊傪柦偠偨帪偺嵾忬偼師偺捠傝偱偁偭偨丅
(塿揷埲壓檤暘偵奐偡傞媍埬)
亀崯搙丂屼壠屼堦戝帠偵棫帄傝岓庯偼丂塿揷塃塹栧夘丂懘奜姯棛嫟摨巙擵幰傪廤丂怺偔搆搣傪寢傂丂昞偼懜墹澋埼偲錴丂泬偼枊晎傪搢擵枾嶔傪埲偰
悈晎懘奜彅斔擵摨巙偲挮崌丂嫗巘傊庢擖丂屼恊惇傪怽寶丂婛偵懘嶔壜旐峴惃偵傕憡惉岓摼嫟丂尦樢枾杁擵媀偵晅丂嫀敧寧廫敧擔擵堦潷弌樢巇丂揤挬
枊晎嫟屼晄庱旜偵憡惉丂屼壠擵屼戝帠娽慜偵岓摼偽丂憗懍夵怱帺岫偟偰屼殸擄偵壜憡懼敜擵檤丂柍懘媀娨偰変堄傪挘丂嵆岓醕幍寧墬嫗巘媦朶摦丂廔偵
挬揋擵墭柤傪旐啜栔丂屼姱埵屼鈏錴丂屼堦帤枠旐啜彚曻丂捛摙巊巐嫬偵旐嵎岦丂幮鈒擵屼埨婋崱擔偵憡敆傝岓抜丂幓奆丂塃塹栧夘丂懘奜姯棛擵強嬈偵
岓摼偽丂揤挬枊晎傊旐啜洈丂愭嫄夽擵暘嵍擵捠壜旐峴殠敱嵠丂扐丂崯搙閾擵戝嵾堷晅岓愭奿傕柍屼嵗岓
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂塿揷塃塹栧夘
塃嵼栶拞姯棛嫟偲搆搣傪寢傃丂屆樢擵屼朄夵妚偵戸偟丂巹堄傪埲屼殸閾傪攋傝丂忚揤挬枊晎傪曁傒丂帺恎擵姊愑憡敆傝岓偵帄偰偼孯徬傪埲嫗巘傪梚偟
嫲偔傕曭嬃泜嬢岓師戞丂峏偵旐嬄暘擵屼庤抜傕柍擵丂廔偵屼殸擄偵帄傝岓抜晄拤晄媊擵帄傝晄堗帠岓丂埶擵愗暊旐嬄晅岓帠亁
丂丂丂丂丂丂丂乮弌揟亖乽杊挿夞揤巎乿戞係曇壓30暸丄43暸丄46暸)
愭偢塿揷塃塹栧夘偲崙巌怣擹偑摽嶳偺憏帩堾偱憇楏側愗暊傪悑偘偨丅嶰恖栚偺暉尨墇屻偼丄摽嶳偺斔庡偑斵偺堎曣掜偵偁偨傞偨傔丄愗暊偺応強傪娾崙
偺棾岇帥偵堏偟偰幚巤偝傟偨丅強偑丄嵾忬撉傒搉偟偑廔傢偭偰傕丄墇屻偑桴偐側偄偺偱専帇栶払偼峇偰偨丅曬崘彂偵偼乽偍惪偗擵柍偒偵晅偒乿偲偁傞丅
偮傑傝墇屻偼嫅愨偟偨偺偱偁傞丅側偩傔偡偐偟偰丄傗偭偲愗暊偝偣偨丅枹楙偑傑偟偄偲偄偆夝庍傕偁傞偑丄墇屻偙偦嵟屻傑偱懎榑攈偵掞峈偟偨壠榁偲
傕尵偊傞丅
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂乮弌揟亖乽挿廈楌巎廍堚乿54暸埲壓乯
乽杊挿夞揤巎乿偼塿揷塃塹栧夘偺嵟屻偺柾條傪師偺傛偆偵弎傋偰偄傞丅
丂亀堦丄斵帥墶嵗晘傊峊嫃岓張丂柍娫巇潓媂抜塿揷鋙堦榊怽弌岓偵晅奺懘奜屼巊斣暔摢抳拝惾丂捈偵塃塹栧夘揳彫屟拝梡偵偰旐旊弌丂奆條屼嬯楯漌偲
旐抳垾嶢屼巊斣嶳揷廳嶌嵾忬彂撉搉擵丂塃塹栧夘揳嬣偱攓挳桳擵丂崱堦滀塃夁幐彂攓尒抳偝偣屶岓條偲偺媀偵晅偒廳嶌傛傝塃塹栧夘揳傊憡搉弉棗憡惉
柍娫旐嵎曉捈條嵟慜擵峊強傊堷庢岓帠
丂堦丄巟搙憡挷巇潓媂抜塿揷鋙堦榊怽弌岓晅恾柺擵捠抳拝惾丂塃塹栧夘揳忯擇枃曑憃傊丂懘忋傊巐広巐曽埵擵敀塇擇廳姉抍傪晘懘忋傊拝嵗憡惉丂摽嶳
屼搆巑敀栘擵嶰曽傊搚婍擇僣崺晍傪忔偣挾巕摍帩弌偟庰嶰專旐撣昄偰嶰曽傊抁搧傪忔偣夘嶖塿揷鋙堦榊塃塹栧夘揳慜傊悩傊丂嵍岓偰嵍榚傊峊嫃岓張娚乆
彅敡傪扙偓墴壓偘丂抁寱傪庢傝懻偒敳曻偟丂嶰曽擵忋巻偵偰嶰曊怈偄丂懘巻傪埲愗愭偒屲暘埵弌偟恘傪姫偒丂壓暊傪晱壓丂抁寱傪媡庤偵帩丂暊堦暥帤偵
憕愗傝丂捈偵帩捈偟堲傪塃傛傝嵍偵撍擇搙墴崬岓張傪塿揷鋙堦榊庱懪棊丂廔偵懪夌媦愨柦丂棫攈擵嵟婜尒撏捈條塃庱媺専抐丂摗堜娭師榊寣傪愻偄庱壉
傊擺傔鋓傊忔偣丂摽嶳暔摢孎扟巙搊旤丂拞娫摢暷揷慞暫塹傊梐抲丂寈塹岦寴屌偵抳岓條憡庼岓偰丂捈條奺懘奜屼巊斣暔摢摽嶳栶恖堦摨嬨僣帪斾憡嵪丂
崙巌怣擹廧嫃強悷愹帥傊旊墇岓帠亁
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂埲丂忋
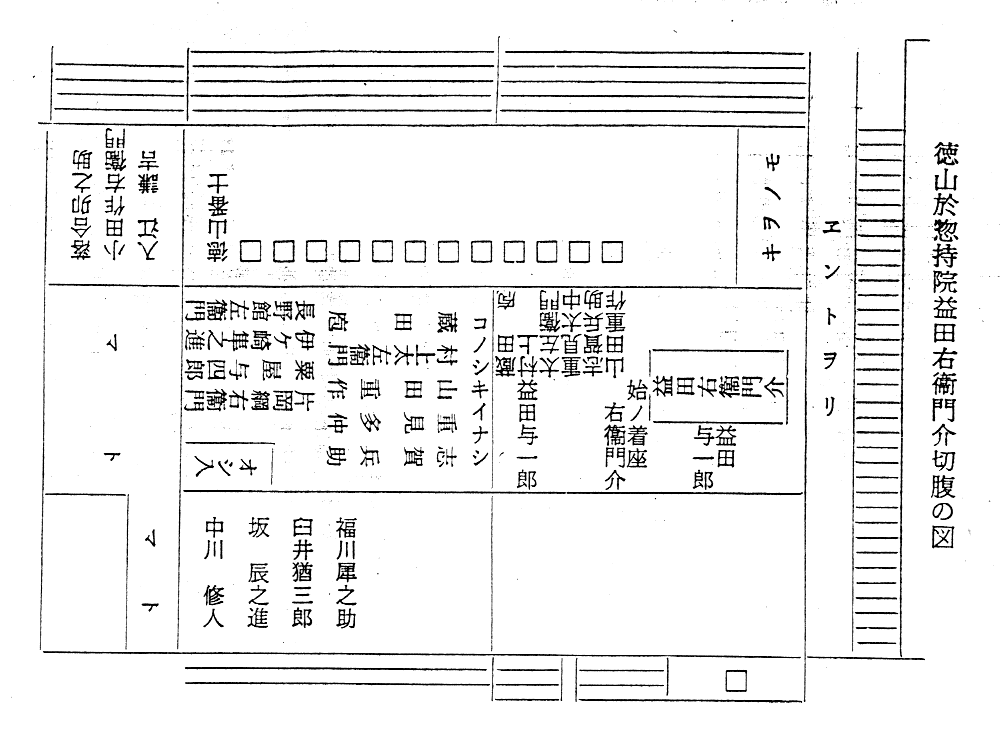
乮丂弌揟亖乽摽嶳巗巎巎椏乿拞 乯
俹係俁
丂仦偁偲偑偒
攇揷梌巗偼恵嵅偵婣偭偨屻丄壠拞惌晎偺梂惌摪偵擖偭偨丅
11寧丄庡恖塿揷塃塹栧夘偑斔偺愑擟傪晧偭偰愗暊偡傞丅庱偺側偄堚懱偩偗偑婣偭偰偒偨恵嵅偱偼丄戝扟烏彆偑弣巰傪婅偄弌偨丅梂惌摪偱偼偙傟傪
偒偭偐偗偵堦攈傪婖傒寵偄撪鎌栤戣傊偲敪揥偡傞丅
戝扟烏彆偼乽夞揤孯乿傪嶌傝丄堦曽壠拞傕乽杒嫮抍乿傪嶌偭偰夞揤孯傪捵偦偆偲偡傞丅枊枛丄夵妚傪傔偖偭偰偳偙偺斔傗壠拞偱傕婲偙偭偨撪鎌栤戣
偱偁傞丅偙偆偟偰攇揷梌巗偼戝扟烏彆傜偲懳棫偡傞偙偲偵側偭偨丅椞庡丄塃塹栧夘傪幐偭偨曣恊(愬憡堾)偲壠拞偼壠柤傪夞暅偡傞帠偺傒偵幏擮傪尒偣丄
昁恵偱偁偭偨夵妚偵忔傝抶傟偨丅
戝扟烏彆摍偼庡恖偵廬偭偰嫗搒傗峕屗偱摥偒丄懡偔偺巙巑偲岎棳偟偨寢壥傪怴偟偄悽奅偵妶偐偦偆偲偟偨丅偟偐偟丄梂惌摪傪摦偐偡戝慻偺巑偼戝扟
烏彆摍偺媫寖側恑庢傪寵偭偨丅帺傜偺夵妚偺棟擮偐傜嶌偭偨夞揤孯偵幏擮傪擱傗偟丄婏暫戉傊擖傞摴傕抶傟偨丅杒嫮抍偼夵妚偡傋偒堄尒傕柍帇偟戝扟
烏彆摍傪斁媡偲偟偰愗暊偝偣偨丅
挿廈嵞惇偑婲偙偭偨丅攱斔偼恵嵅壠拞偺撪鎌傪張暘偟丄攇揷梌巗傜忋憌晹偼椞奜塀嫃傗墦搰偑寛傑偭偨丅嬛栧偺曄偐傜堦擭屻偺帠偩偭偨丅
尒抦傜偸搚抧偱偼側偐偭偨偑丄梌巗偼晄帺桼側惗妶傪梋媀側偔偝傟偨丅梻擭偺壞丄梌巗偼挿廈嵞惇偺孯椷彂側偳偑旘傃岎偭偰偄傞偙偲傪樅偐偵暦偒丄
戝朇戉偑嬤偔偺摴傪愇廈偵岦偐偭偰堏摦偟偰偄傞偙偲傪暦偄偨丅娫傕側偔梌巗偼嵾傪嫋偝傟偰婣戭偟偨偑丄擱從偟摼側偐偭偨恖惗傪峫偊偨丅
偦傟偐傜娫傕側偔梌巗偼巰傫偩丅 嶰廫榋嵨偲偄偆庒偝偩偭偨丅
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂忛堦丂徍恖丂婰
俹係係
丂仦曇廤屻婰
仠暯惉9擭5寧丄憹栰椇偝傫偺壒摢偱嶳岥導垻晲孲恵嵅挰弌恎偺6恖偺摨岲偺儊儞僶乕偑搶嫗怴廻偺乽崱敿乿偵廤傑傝乽搶嫗恵嵅巎択夛乿偑敪懌偟傑
偟偨丅儊儞僶乕偑強憼偟偰偄傞屆暥彂丄屆抧恾丄壠宯恾丄偦偺懠偺帒椏傗忣曬傪岎姺偟側偑傜徟揰傪枊枛堐怴帪戙偺恵嵅嫿搚巎偵峣偭偰曌嫮偑巒傑傝
傑偟偨丅嵟弶偼3儢寧偵1夞掱搙偱偟偨偑丄嵟嬤偼寧1夞掕椺尋媶夛傪奐偔傛偆偵側傝傑偟偨丅1擔5帪娫偺曌嫮偼忛堦掕偝傫丄忛堦徍恖偝傫偛孼掜偺偛巜摫
偱偙傟傜偺恵嵅娭楢偺屆暥彂傪撉傒丄堄尒傪岎姺偟丄偦傟偑偳傫側帪戙偩偭偨偺偐丄恖偼偳傫側傆偆偵惗偒偨偺偐丄側偳傪擬怱偵榖偟崌偭偰偍傝傑偡丅
寬峃栤戣傗偛崅楊偺堊偵戅夛偝傟偨曽偑2柤偁傝傑偟偨偑丄夛堳悢傕彊乆偵憹偊偰崱偱偼9柤偺曽乆偑嶲壛偝傟偰偄傑偡丅
仠暯惉14擭偺偁傞擔丄枅夞堄尒岎姺偟偨忎偱廔傞偺偼栜懱側偄丅愜妏偺尋媶夛偺惉壥傪嬶懱揑側宍偱巆偣側偄偩傠偆偐偲偄偆媍榑偑婲偙傝傑偟偨丅
偦偺寢壥丄偦傟傑偱偵尋媶偟偨巎椏偺拞偐傜廳梫側傕偺傪慖傫偱丄柸枾側拲庍傪巤偟弌斉暔偵揨傔傛偆偲偄偆帠偵堄尒堦抳偟傑偟偨丅恵嵅挰偱傕嫵堢埾堳夛
偺偛巟墖偺壓偵乽恵嵅挰嫿搚巎尋媶夛乿偑妶摦偝傟偰偄傑偡偺偱丄搶嫗偺変乆偺尋媶惉壥傕恵嵅偺婡娭帍乽壏屘乿偵嵦梡偟偰捀偗側偄偩傠偆偐偲尵偆埬傕
偁傝傑偟偨偑丄壗偼偲傕偁傟嬶懱揑側惉壥傪弌偝側偄帠偵偼偛憡択傕弌棃傑偣傫偐傜丄庤巒傔偵乽悘峴擔婰乿偺夝撉傪偟偰傒傛偆偲偄偆帠偵側偭偨偺偱偡丅
乽悘峴擔婰乿偼恵嵅挰偐傜尕傜偝傟偨暋幨僐僺乕傪暅崗偟偨傕偺偱偡丅
仠乽悘峴擔婰乿偺尋媶偱偼師偺傛偆側媍榑偑岎傢偝傟傑偟偨偑丄栤戣採婲偵偲偳傑傝傑偟偨丅
堦丄丂敻屼栧偺曄偵嵺偟偰丄挿廈斔偼3恖偺壠榁偲惓婯孯傪忋嫗偝偣側偑傜7寧17擔抝嶳偺愇惔悈敧敠媨偺孯媍偱棃搰枖暫塹丄恀栘榓愹摍彅戉偺嫮峝榑
傪梷偊傞帠偑弌棃側偐偭偨丅壗屘偐丅捄柦偼婾捄偩丅嬑墹偺斔庡晝巕偺墭柤傪愥偖堊偵偼孨懁偺汙傪彍偔傋偟丄挬掛偺戅嫀婜尷偑7寧18擔偲捠抦偝傟偨埲忋丄
悽巕忋嫗屻偺峴摦偼庡孨偺婋婡偲側傞丅戅嫀婜尷偺柧擔抐屌帺恎偺愑擟偱晲栧偺柺栚傪娧偔偲偄偆夁寖攈偺堄尒傪扤傕梷偊偒傟偢丄寢嬊丄挿廈暫偼嶰曽柺偐傜
夛捗斔庡徏暯梕曐偑嫃傞嬅壺摯傪栚巜偟偰恑寕偟傑偟偨丅攚宨偵偼暅尃傪慱偆屲嫧偺埑椡傕偁傝傑偟偨丅愴摤偼嶰曽柺晇乆偺楢実偑埆偔奺屄寕攋偝傟嶴攕偟丄
嫇偘嬪偺壥偰偵屼強偵岦偐偭偰敪朇偟偨挿廈斔偼挬揋偺墭柤傪栔傞偙偲偵側偭偨偺偱偡丅斔惌晎偼壠榁偵崟報偺孯椷忬偲偄偆晲椡峴巊偺尃尷傪梌偊偰偍偒側偑傜丄
澋埼扱婅丄楾錝幰慒嶕丄屲嫧傗栄棙晝巕偺檒嵾垼慽側偳偺惌帯岺嶌偑幐攕偟偨偲偒偺柧妋側愴棯傪寚偒曽恓偑濨枂偱廳梫側敾抐傪尰応擟偣偲偟傑偟偨丅
尰応偼挸棯傕懪偰偢丄嫗搒偺抧棟傕枮懌偵敾傜偢丄愘楎側愴摤偵偺傔傝崬傫偱峴偒傑偟偨丅怣挿丄廏媑丄壠峃傗尦廇丄婸尦偺帪戙偼庡孨偑帺傜愴傪恮摢巜婗
偟傑偟偨丅偦傟偐傜300擭帪戙偑壓偭偰懢暯偵姷傟偨枊枛枊斔懱惂偺壓偱偼丄偳偺斔偱傕斔惌晎偼姱椈壔偟偰愴崙偺椪愴懱惂偐傜暯帪懱惂傊偲惌帯慻怐偑曄杄
偟偰偄傑偟偨丅偄偞愴偲側傞偲丄斔庡傪愴憟愑擟偐傜庣傠偆偲偡傞慻怐偵曄幙偟偰偄傑偟偨丅
堦丄丂塿揷恊巤棪偄傞暫600偺堦晹偼嶄挰屼栧偺愴偵嶲愴偟巆傝偼屻媗傔偲偟偰揤墹嶳偵巆傝傑偟偨丅斵偼丄攕愴偺抦傜偣傪暦偄偰偳偺傛偆偵敾抐偟偨偺偐丅
塿揷扥壓偑堷偒梘偘傪恑尵偟偰傕拠乆寛怱偑晅偐側偐偭偨條偱偡偑丄偮偄偵堦愴傕岎傞偙偲側偔丄嬐偐側偍嫙傪楢傟偰崙尦傊堷偒梘偘偨偲偄偄傑偡丅
偙偺娫偺帠忣偼晄徻偱偡偑丄慡懱傪捠偠偰塿揷恊巤偺巚憐偼暿搑崱屻偺廳梫側尋媶壽戣偲偟偰尋媶偡傞昁梫偑偁傞偲偺寢榑偵払偟傑偟偨丅
堦丄丂巹払偼師偺3偮偺棟桼偐傜乽悘峴擔婰乿偼昅幰偺攇揷梌巗偑恵嵅偵婣偭偨屻偵庢傝揨傔偨傕偺偲敾抐偟傑偟偨丅
仦杮恮偑偁偭偨乽曮帥乿傪乽妢帥乿偲岆婰偟偰偄傞丅
仦奐愴偺擔晅傪岆婰偟偰偄傞乮堄恾揑偵夵鈧偟偨偺偐傕乯
仦帥偺柤慜偑敾傜側偔側傝乽幐帥柤乿偲婰偟偨儢強偑2儢強偁傞丅尰応偱彂偄偨擔婰側傜暦偗偽敾傞敜丅傑偨丄恮応曭峴偑帺孯傪攝抲偟偨応強傪朰傟傞帠偼
偁傝摼側偄丅慜屻偺暥柆偐傜敾抐偟偰偙傟傜偼棧媨敧敠媨偺幮揳傗曮帥偺憁朧偺堦偮偱偼側偄偩傠偆偐丅崙尦偵堷偒梘偘偰巇晳偭偨偺偱幮揳傗憁朧偺柤慜傪
妋偐傔傞帠偑弌棃側偔側偭偨偺偩傠偆偲悇應偟傑偟偨丅
堦丄丂乽悘峴擔婰乿偵傛偭偰恵嵅暫偺攝恮偺柾條偑柧傜偐偵側傝傑偟偨丅偟偐偟丄嶳嶈偲抝嶳偵偼挿廈孯慡懱偱偼傕偭偲戝偒側暫椡傪抲偄偰偄傑偟偨丅 偦偺徻嵶偼敾傝傑偣傫丅乮8暸*1嶲徠乯
堦丄丂敻屼栧偺曄偱戝嶳嶈偱偼杦偳偺恄幮暓妕偑從偒暐傢傟傑偟偨丅抝嶳偼壩嵭傪柶傟偨偑偦偺屻偺曡扖愴憟偱壩嵭偵憳偄丄柧帯偺攑暓毷庍偱杦偳偺憁朧偑
攋毷偝傟傑偟偨丅廬偭偰姫摢偵宖偘偨幨恀(HP斉偱偼幨恀偼徣棯偟傑偟偨)偺擛偒崱擔変乆偑栚偵偡傞杦偳偺恄幮暓妕偼墲帪偺巔偲偼堎側傝傑偡丅
仠埲忋偺條偵婔偮偐偺戝偒側尋媶壽戣偑巆傝傑偟偨偑丄巹払偺乽悘峴擔婰乿偺尋媶惉壥偑彮偟偱傕偍栶偵棫偮側傜偽朷奜偺岾偄偱偡丅
丂丂丂暯惉16擭4寧
丂丂丂搶嫗恵嵅巎択夛
丂丂丂丂丂丂丂丂撪摗丂搊
丂丂丂丂丂丂丂丂忛堦丂掕
丂丂丂丂丂丂丂丂憹栰丂椇
丂丂丂丂丂丂丂丂惔抧丂帯惓
丂丂丂丂丂丂丂丂孖嶳丂揥庬
丂丂丂丂丂丂丂丂朙揷丂徏晇
丂丂丂丂丂丂丂丂嬤摗丂埨峅
丂丂丂丂丂丂丂丂忛堦丂徍恖
丂丂丂丂丂丂丂丂戭栰丂岹
丂丂丂丂丂丂丂丂徏堜丂嶰榊
丂丂丂丂丂丂丂丂懡崻丂媊崉
乮埲忋偼乽悘峴擔婰乿偺尋媶偵嶲壛偝傟偨搶嫗恵嵅巎択夛偺慡儊儞僶乕偱偡乯
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂孖嶳丂揥庬丂婰

|