会誌「温故」 |
|
「温故」第7号須佐郷土史研究会 |
|
| TOP PAGEへ | 「温故」総目次へ |
| ||
会誌「温故」 |
|
「温故」第7号須佐郷土史研究会 |
|
| TOP PAGEへ | 「温故」総目次へ |
| ||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P3 | |
調 書
|
| P4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 5〜9 此処をクリックして下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 四境戦争の記録 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
七月十五日(慶応2年=1866)日の出より戦始まり長州精鋭隊并に一番二番大隊之内三中隊大麻山へ押出寄せ戦争はげしく終に
大麻山を乗取る。 此大麻山と申は兼て敵兵籠城之地にかまへ申候所也。浜田、福山の両勢防禦に術を失ひ七條村へと志し後をも見ずして落ち行ぬ。此所迄浜田城下より三里程有之在也。 はげしくも攻附られて白泡を吹く山坂を丸腰にして爰にて分捕もの左に記す。 白米弐百俵 酒四斗樽四挺 この時西村と申所へは大隊之内弐中隊無二無三に押寄せたやすく四つ門を打崩し其時精鋭隊猶豫なく大麻山より烈風のごとく 押おろし |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鯨波(とき)を作りてせめ寄せしに忽敵兵敗走す。 和歌山の色青ざめし葉武者とて 太刀風吹けば散るぞ本意なき
十六日早天より精鋭隊并に清末育英隊三中隊西村関門口より大隊之内二中隊押出し周布村(現浜田市)門田村と申三ヶ所之村
へ紀州勢踏止まり、陣所をかまへ扣(控)たり。それと見るより長州勢神納山より押おろし日の出頃より戦はじめ、敵兵そこにて
不覚をとり今や恥辱を雪(すすが)んと大砲小銃きびしく構へ、打出す事おびただし。すきを見合い長勢われ劣らじと押寄せしに、
爰にも敵兵たまり得ず周布川まで敗走す。此時内田村に扣(控)し雲州勢も南園隊と対陣にて打出す砲声百千の雷の轟くがごとく
三時の間止まざりし。南園隊は面白き叓(こと)におもひ、中にも不敵の若武者は打ぬかれたる似(まね)をして倒るるが否
敵方には打留めたりと歓びて声をたつれば、かわ(がば)と起き爰をうてやと後むきあざむけつなぶりつしては時移る。 堅陣と思いの外の後詰する 人もなくなく延(逃)る敵かな |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西村、周布村、門田村此の三ヶ所の分捕もの左に記す。 メリケンホヲト 五挺 十七日八ツ時(午後二時)浜田より使番来り和儀を乞といへども、是等の叓(こと)に付ては家老重役差越され候はでば不相調 (あいととのはず)段と申懸られ一応使者相帰り翌十八日に至り候ても何たる返答も無之此日昼頃より浜田城内并に家中居屋敷 残らず放火焼捨に致し候。尤前日家中之面々へは分限に応じ配金有之、町家へは家別に三歩二朱宛配当致され浜田侯并に家中 之面々不残因州雲州一同に因州さして落行けり。哀といふも疎(おろか)なり。紀州福山の残兵周布川迄落延しが渡る可き船 壱艘もなく、兵糧には尽果て、波子(現浜田市)の浜と申所にて数多餓死におよびたると聞く。 哀れさよ修羅のちまたはのがるれど また餓鬼道におつるはかなき 城下にて分捕もの左に記す。 黒米 壱万俵 金子五箱 尤一箱丁銀有之 又十五日より十八日迄戦争、味方怪我人なし。尤死人壱人有之、是は育英隊之内也、敵方死人怪我人数不数。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 古文書によく出る言葉について(1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
私たちが吉文書を読んでいると、いろいろわからぬ言葉がでてきます。このたび山口県文書館の石川卓美氏が、何十年という努力のすえ
「防長歴史用語辞典」を大成されました。一冊が一万五千円もする大作ですが、私たちが手にするにはちょっと荷が重すぎます。それで、
私達が古文書を読みながら、その中によく出てくる言葉や郷土史研究上よく見聞きする言葉をひろって紹介することにします。 これは石川先生の御了解もいただいております。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 須佐周辺の城砦跡 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山口県未指定文化財の内、城砦調査でいろいろ調査したものを、事務局がまとめてくれました。戦国期、益田氏と津和野吉見氏の勢力の接点であったこの地方
は、一朝にして彼我所をかえるような激戦がくりかえされた所でした。 山ロ県は昭和55年から県内の未指定文化財について、総合的に調査し基本台帳を作成し、さらに貴重なものについては指定を図り保存対策を講ずることを目的に 調査概要を発表しました。 須佐周辺の城砦跡調査は郷土史研究会、町文化財保護審議会が昭和58年から同59年に実施、須佐地区では笠松山城(磯ケ崎城)、懸の城、犬伏山城、弥富地区では 敵陣ケ嶽城、遠田城、茶臼山城、鈴野川地区では火の谷城(津和野町では御嶽城)の7ヶ所があります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
笠松神社に下車、山陰本線を横切り20分登る。山頂(標高98米)は平坦地、四方は急峻、北は須佐湾、南は町内、東は懸けの城、犬伏山城が一望できる。 はじめ吉見氏の出城でのち磯ケ崎城と呼ばれ、永禄5年(1562〉吉見正頼が須佐に侵入した時、益田兼貴は大激戦の末、この地を守ったと益田家茂の書に残されている。 ー防長風土注進案ー |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
須佐駅背後の山頂(標高80米)まで15分登る。益田家の出城で南北に細長く東は犬伏山城、西は笠松山城を望み、
磯崎城で活躍した寺戸大学が拠ったと伝えられる。西麓の
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
竹林には益田家と吉見家の激戦を偲ばせる三界万霊等碑がある。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
帆柱原田芳夫氏住宅の裏山尾根を30分登る。途中はシダが深く山頂は雑木が繁茂しており
調査は困難を極めた。山頂(118米)は平地で三段、城建築時に用いたと思われる基礎石と井戸跡が確認できる。
江津側には堀切、三方は急峻、西側は懸の城、笠松山城が一望できる。益田氏の出城で小原東蔵人が拠ったと伝えられる。
ー防長風土注進案ー |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
鈴野川からの登山は不可能なため津和野町長野地区の愛宕神社より登る。
目的地までの所要時間は1時間40分、山頂(標高504米)は南北に58米、本丸・
二の丸・三の丸東は90米さきに出丸があり、四方は急峻で難攻不落である。吉見顕彰会建立の石碑に
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
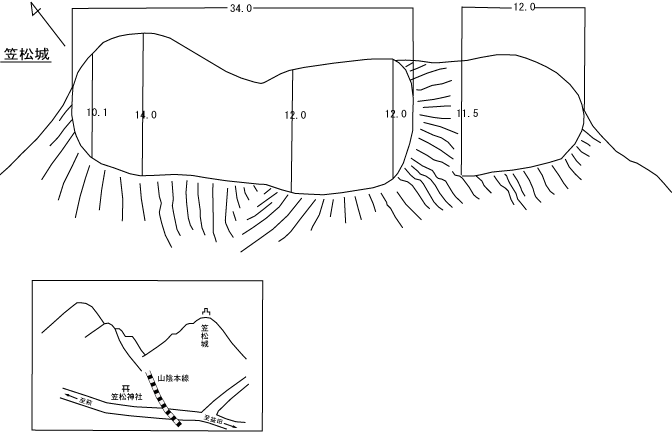
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
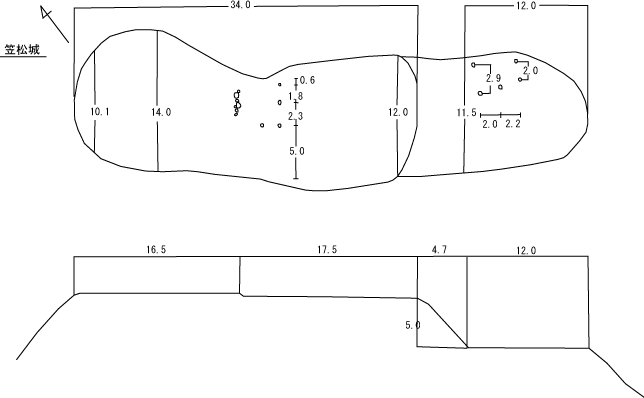
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
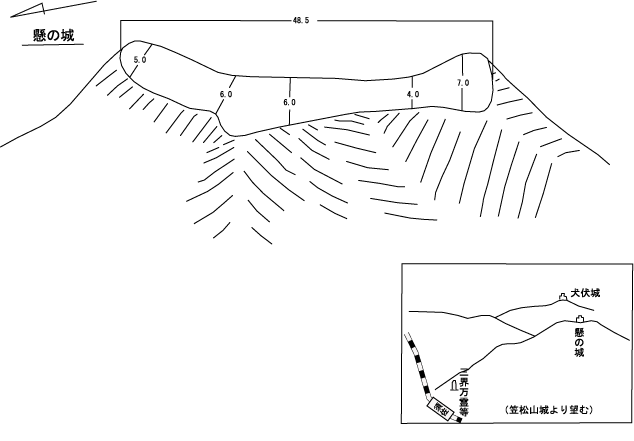
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
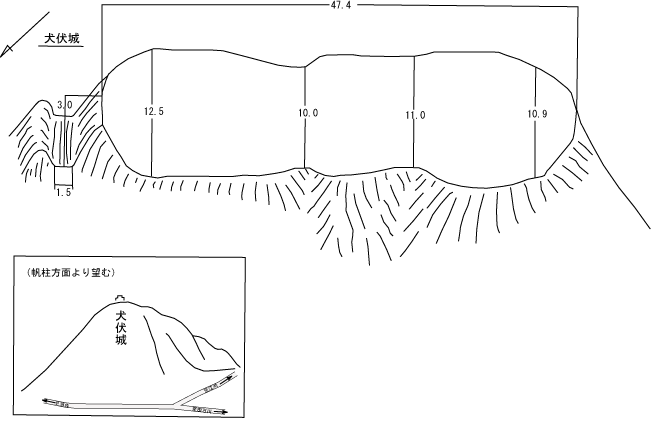
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
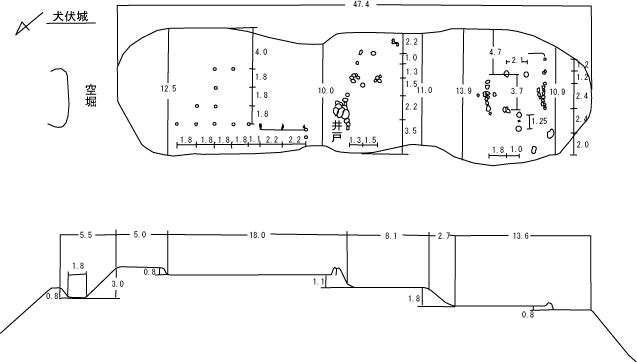
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「頼行公入部して12年間の本城であった、弘治元年(1555)陶軍を迎入れ一族岡頼照対陣籠城の跡である」とある。
現地からは鈴野川、弥富、小川、遠くは須佐高山や日本海が望める。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
落山より軍場を通り急峻を40分登る。山頂(標高360米)は平地で中央に石祠2ヶ所があり、樹齢約60年と思われる榊が 一対植えてある。石祠並びに石垣に使用の石は城建築時の基礎石と思われる。平山城側に2つの出丸、河内側には堀切がある。 天文22年(1553)大内義長が津和野三本松城を攻めた時、その将町野隆風が阿武郡を攻略しており、 後に星の城をもって吉見正綱に降伏している。注進案に搦手より攻め |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
落城したとあり、城兵の逃れた所を落山、城の麓を城ヶ谷、河内の上の山を敵陣ヶ嶽とし今も地名が残る。落山、城ヶ谷から一万にかけて 城兵軍馬等が多数討死したと伝えられ、一万の端に野ずら石で三界万霊等碑が建てられている。
☆遠田城
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西秀寺裏の山道を10分登る。山頂(260 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
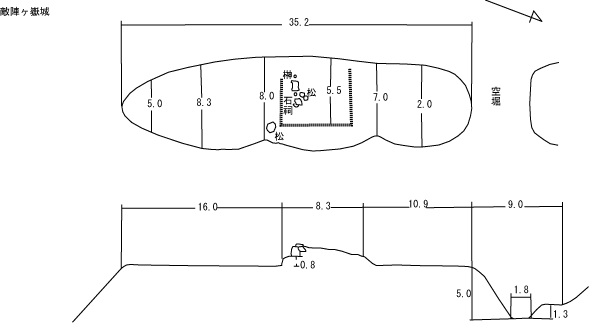
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
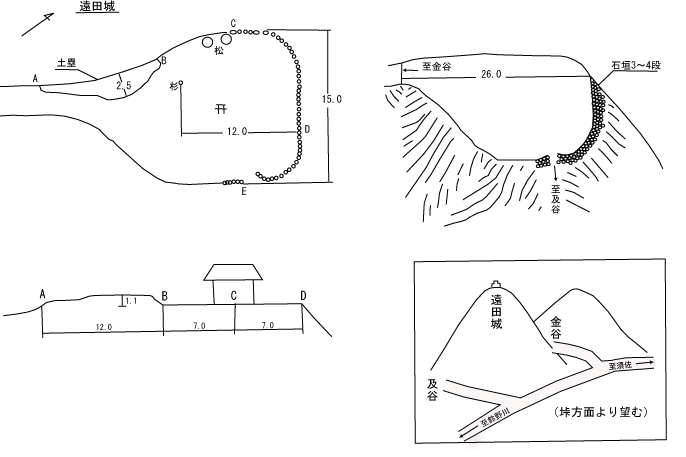
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
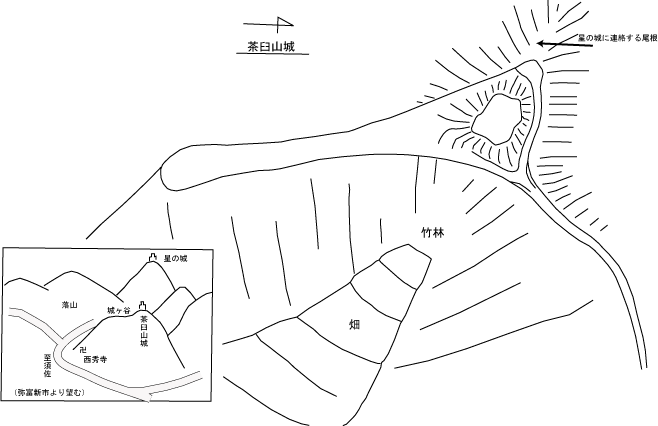
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヶ山城(田万川町)、遠田城が一望できる。口伝によると東側尾根を馬をひいて一万まで水を汲みにいったとある。尾根は比較的緩やかで口伝も まなり信憑性がある。
この外に弥富地区では土井、炭山城、要害ヵ嶽城(天守ヵ嶽城)の3ヶ所が上げられ、土井は弥富六区の山根梅信氏住宅周辺が地名で、山口県風土誌 「按るに土居の誤なり。由来書に土井と申畠有之、此畠往古敵陣の城主屋敷跡と申伝候と見ゆ」とあり、また炭山城は「弥富上村の炭山、山谷の間」、 要害ヵ嶽城は「弥富下村の蒲原」とあり、今後の調査を要します。 参考文献 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 竹篭類の製作寸法 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総テ仕事ヲナスニ当リテハ先ズ計画ト準備トヲ要ス、若シ夫レ之レカ計画ヲ誤リ準備ニ於テ欠クル所アランカ即チ其ノ結果ニ至大ノ関係ヲ
有シ無駄ノ費用モ労力モ時間ノ空費モ茲ニ始メテ生ズルモノト知ルベシ
材料ノ選択 材料の取り方 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
着色法一般
竹材着色ニ祟リテハ留意スベキハ竹材ノヨク乾燥セルモノ又ハ油抜ヲセルモノニ染色スルヲ肝要トス、之染料ノ竹材ニ及ホス染着力ヲ大ナラシムル
タメナリ。 ビスマークブラウン(茶粉)、マラカイトグリーン(青竹)、オーラミン(黄)、ダークブルー(暗青)、メチールブアイオレット(紫)、ローダミン(赤) 1。加工品着色法
本法ハ主トシテ花生篭類其他書類入等各種ニ応用スベキモノナリ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 目 次
目 次品 名 頁 六ツ目組方 1 煮 篭 2 果 物 篭 3 茶 碗 篭 4 盃 伏 篭 〃 陸 持(オカモチ)篭 5 水 垂 〃 箸 入 6 味 噌 濾 〃 箕(ミ)(横目) 7 〃 (縦目) 8 石 笊 9 石 炭 篭 〃 飯 取 篭(円蓋付) 10 飯 取 篭(角) 11 大 笊(ザル) 12 八百屋篭 13 麦 酒(ビール)篭 14 手 保(テモチ)(四ツ目底) 15 手 保(菊底) 16 桑 摘 (クワツミ)篭 17 炭 取(スミトリ) 18 竹細工用工具一般 19 竹細工用工具一般 20 竹材並加工品 21 着 色 法 22 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
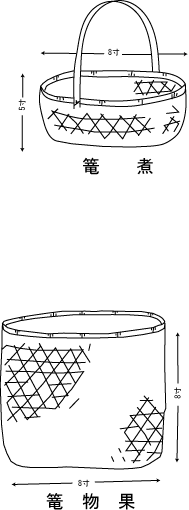 (1)製作寸法(皮製)
(1)製作寸法(皮製)底組竹ノ長サ 1尺3寸 幅2分5厘 数24本 底ノ組幅7寸 廻竹ノ長サ2尺8寸 幅2分5厘 数3本(2)標準価(小売値ハ卸値ノ1割5分増 以下準之) 卸値 11銭5厘 内材料費 5銭 (1)製作寸法(身皮製) 心竹ノ長サ 横2尺4寸 縦3尺5寸 割幅1分7厘 横20本 縦三本 廻竹ノ長サ 3尺2寸 幅1分7厘10本(2)標準価 卸値 5銭 内材料費 2銭 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
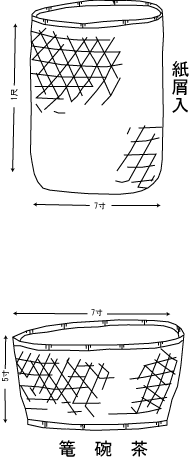 (1)製作寸法(皮製)
(1)製作寸法(皮製)底組竹ノ長サ 3尺5寸 幅2分5厘 数30本 底組幅 7寸 廻竹ノ長さ 2尺8寸 幅2分5厘 数12本(2)標準価 卸値 26銭 内材料費 15銭 (1)製作寸法(皮製) 底組竹ノ長サ 2尺 幅2分 数30本 廻竹3尺3寸 幅2分 数6(2)標準価 卸値 30銭 内材料費 16銭 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
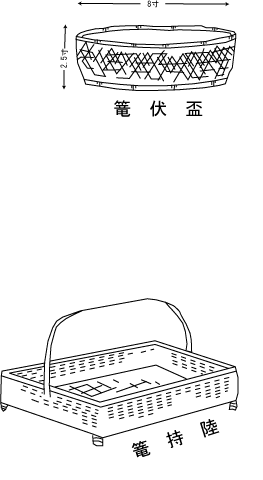 (1)製作寸法(六角形)
(1)製作寸法(六角形)底組竹 長1尺4寸 幅1分 数 48本(2)標準価 卸値 21銭 内材料費 10銭 (1)製作寸法 心竹ノ長サ 縦1尺3寸 数11本 横1尺1寸 数14本 幅4分 底組幅ハ 縦8寸 横6寸 高1寸8分(2)標準価 卸値 20銭 内材料費 7銭 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 (1)製作寸法(皮製)
(1)製作寸法(皮製)心竹ノ長サ 1尺3寸 幅4分 数30本(2)標準価 卸値 40銭 内材料費 14銭 (1)製作寸法(菊底) 心竹ノ長 1尺3寸 幅4分 数6本(2)標準価 卸値 15銭 内材料費 5銭 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 (1)製作寸法(皮製)
(1)製作寸法(皮製)心竹ノ長 1尺4寸 幅4分 数14本
(2)標準価 卸値 26銭 内材料費 10銭
(1)製作寸法(横目3尺2寸) 台輪ノ長 3尺2寸 幅4分 数1本
(2)標準価 卸値 50銭 内材料費 20銭 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
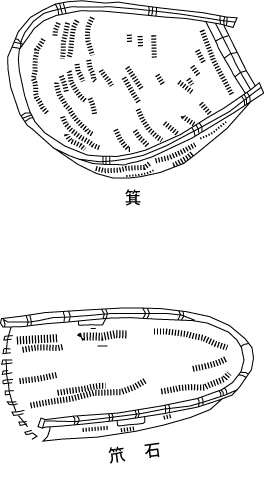 (1)製作寸法(縦目3尺2寸)
(1)製作寸法(縦目3尺2寸)台輪ノ長 3尺2寸 幅4分 数1本
(2)標準価 卸値 55銭 内材料費 22銭
(1)製作寸法(石ソーケ) 台輪ノ長 3尺7寸 割幅3分5厘 数1本
(2)標準価 卸値 28銭 内材料費 9銭 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 (1)製作寸法
(1)製作寸法心竹ノ長 3尺 幅3分5厘 数24本(但皮2本並べ用フ)
(2)標準価 卸値 35銭 内材料費 15銭
(1)製作寸法(丸形蓋付) 台輪ノ直径 1尺1寸5分 長4尺1寸1分 内合口 5寸 幅3分
(2)標準価 卸値 1円 内材料費 42銭 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 (1)製作寸法(角)
(1)製作寸法(角)台輪ノ長 3尺6寸 幅2分5厘 数1本
(2)標準価 卸値 60銭 内材料費 20銭
(1)製作寸法(ソーケ) 台輪ノ長 5尺5寸3分 幅3分 数1本
(2)標準価 卸値 90銭 内材料費 40銭 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
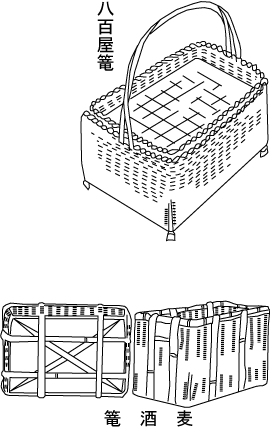 (1)八百屋篭製作寸法
(1)八百屋篭製作寸法(縦7寸5分 横5寸5分 高3寸5分) 心竹ノ長 1尺6寸5分 割幅3分 縦10本 横1尺3寸 横13本
(2)標準価 卸値 35銭 内材料費 10銭
(1)製作寸法 縦心竹ノ長サ 3尺7寸 横 3尺4寸 幅7分 数縦10本 横10本
(2)標準価 卸値 1円20銭 内材料費 37銭 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 (1)製作寸法
(1)製作寸法(四ツ目底底6寸角) 心竹ノ長 2尺8寸 幅3分
(2)標準価 卸値 45銭 内材料費 20銭
(1)製作寸法(菊底) 心竹ノ長 2尺6寸 幅3分5厘 数16本
(2)標準価 卸値 45銭 内材料費 20銭 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP PAGEへ | 「温故」総目次へ |
|
|